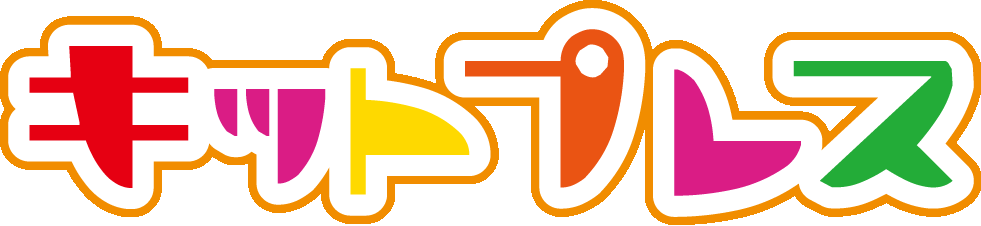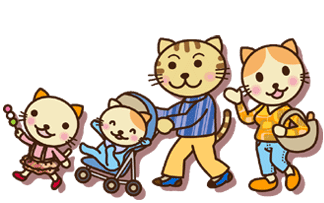いつか世界に認めてもらえる、そんな映画を撮りたい

File.136
監督・演出
いずはら こういち
泉原 航一さん [東京都在住]
公式サイト: https://www.facebook.com/izuhara.kouichi

1987年 岸和田市出身
2007年 大阪芸術大学短期大学部卒業 フリーの助監督として東映に
2012年 映画「黄金を抱いて翔べ」で井筒和幸監督と出会う
2013年 自主制作映画「祭に咲く花」で初監督
人生には“運命”としか思えない出会いがある。
高校生の時、テレビでふと目にした映画「岸和田少年愚連隊」。
若かりし日のナインティナインが、岸和田を舞台にヤンチャしまくる青春グラフィティーに、一瞬で心を奪われた。
「あ、映画監督になりたい――そうヒラメいたんですね。これが誰のどんな作品かなんて、全然知らなかったんです」
ヒラメキを信じて飛び込んだ映画の世界。そこで奇しくもあの映画を撮った井筒和幸監督に出会い、今ともに仕事をしているという、この奇跡。
「井筒さんはパワーにあふれたスゴイ人。映画の持つ力って何なのか、どんな想いで映画をつくらなアカンのかを真剣に考えさせてくれたんです」
運命を信じて跳ぶか、それとも留まるか…どちらを選ぶかで人生は、そこから大きく動き出すのだ。
憧れの井筒監督との出会い
本当に偶然だった。
工業高校の2年生、そろそろ進路を考えないと…ちょうどそんな時だった。
「あの日テレビつけてなかったら、全然違う仕事してたはず…」
映画「岸和田少年愚連隊」――そこには自分が育った町が、画面いっぱいに映し出されていた。チュンバ(矢部浩之)と親友の小鉄(岡村隆)らが繰り広げる、あけすけな泉州弁の応酬の向こう側に、この町の人情が透けて見えた。
「これや!映画監督になりたい」
なんの保証もなかったが、ヒラメいたからには走るしかない。
大阪芸大短期大学部の映画コースに進み、卒業と同時に上京。トントン拍子に東映でフリーの助監督として、スタートを切ることになる。
人気番組「仮面ライダーキバ(テレビ朝日)」のスタッフとして採用されたものの「カチンコのタイミングひとつわからない、まさにゼロからの出発。助監督のスキルをイチからここで学ばせてもらったんです」
それから1年ここで撮影を経験するが「自分の撮りたいものと違う気がして」外れることを決意。バイトでなんとか食いつなぎながら、フジテレビの月9や様々なドラマに携わっていた。
「その間もずっと井筒監督に会いたい、一緒にやりたいってところ構わず言いまくってたんですよ。そしたら偶然知り合いから話が来て、井筒さんが映画撮るから一緒にやれへんかって」
とりあえず口にしていた夢が、一気に現実のものに。上京から数年、あの日人生を変えた井筒監督と、ついに仕事ができる時がやって来たのだ。
作品は作家・高村薫の人気サスペンス小説を映画化したもので、2012年に公開された「黄金を抱いて翔べ」。妻夫木聡主演で、6人の男たちが企んだ金塊強奪計画を描いたものだ。
だが初めて参加した“井筒組”の、あまりのハードさは想像をはるかに超えたものだった。「もう死ぬんちゃうかなって、何度も思った(笑)」
助監督にも4ランクあるのだそう。まずチーフがスケジュールの管理、セカンドが衣装。サードが美術関係、そして最後がすべての雑用から監督の身の回りまで引き受けるいわば何でも屋。彼が担当したのは、もちろん一番キツい4番目のワクだった。
「大阪と東京での撮影中、24時間ずぅぅっと井筒さんと一緒!昨日の反省、今日の撮影の段取り、明日の準備…忙しいわ怒られるわ、もうとにかく寝る時間がないんですよ。2ヶ月間ホテルの部屋まで一緒やから、休める場所も無い。それでも監督のパワーたるやスゴくて、疲れを知らないというか。こっちはもうこのままやと死ぬかも、ヤバいって本気で思いましたもん」
地元を巻き込んで撮った「祭に咲く花」
意識が飛ぶほどのハードワーク。だがその剣ヶ峰を気力で乗り切ってみると、監督との間には師弟のような絆ができ上がっていた。
「次の仕事でも1年かけて、企画から始まってシナリオ、ロケーションハンティング、撮影、編集まで、監督業のすべてを教えてもらったんです。台本をどこまで掘り下げて理解するか、人間の奥にある何を表現したいのか…井筒さんはとことん追求していくし、妥協しない。映画を創るってこういう事なんやなあと」
一方で「25歳までには絶対撮ろう!」と決めていた、自主制作映画「祭に咲く花」を3年前に完成させた。
岸和田のヤンチャくれだった自分だからこそ撮れる物語――15歳の少年たちが悩みを抱えながらも未来に向かうさまを、だんじり祭の高揚や一体感とリンクさせて描く青春映画だ。
「祭にあわせて撮影したので、2週間で一気に撮りきりました。キャスト、スタッフ全員僕の実家でざこ寝、合宿みたいなもんです。けんかのシーン撮ってたら警察がとんできたりとか、またその警官が僕のツレで『久しぶりっ』てなったりとか(笑) この町ならではの濃くて、楽しい撮影でした」
地元で開催した上映会は、どこも観客でギッシリ。
「みんなに喜んでもらって、2年かかったけど作って良かったなあって。今度は30歳までに、スポンサーがつく商業映画を撮るという目標を達成せんと。あと1年半ぐらいしかない、ギリギリです(笑)」
そして夢の向こうに見ているのは“世界”という舞台だ。いつか海外で評価される映画を撮りたい…
ここ十年を見ても「おくりびと」「そして父になる」など海外で称された作品は、ほんのひと握りしかない。
「今日本でヒットする映画は、若いコ向きのわかりやすい単純な映画ばかり。大人がお金を払ってまで映画館に足を運ぶかというと、そら無理やろと」
「ほんまは世界中が楽しめる『007』みたいな映画も作ってみたい。でも日本ではそこまでのお金も時間もかけられないんですよね。だったら例えばクリント・イーストウッド監督の『グラントリノ』みたいに、国を超えて心を揺さぶるような映画を撮ってみたいんです」
井筒監督がかつてインタビューで「観ている人の人生を変えてしまうほどの熱量がある、これこそ映画だ」と答えている。
人生を変えるほどの、マグマを抱いた映画をどう生みだしていくのか、魅せるのか―――泉州発の若き映画人が、これからどんな風に化けるのかとても楽しみだ。
2016/6/19 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔