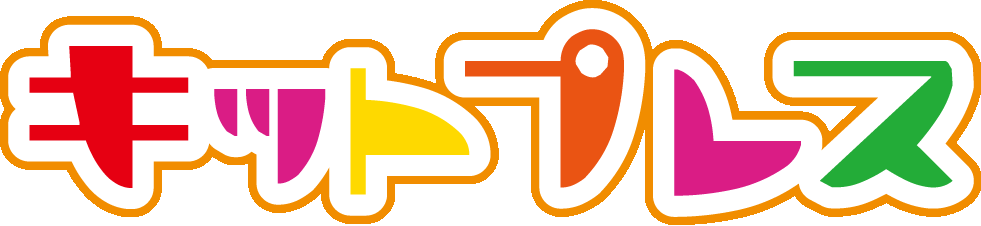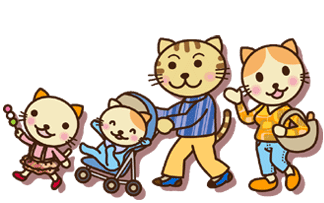自分らしい最期を選択できる、そんな温かい街をめざして

泉北にホスピス病棟を!―――
そんなアツイ思いで「ウィル」を立ちあげて14年。
多くの患者や家族の悩みに寄り添い、時にサポートする彼女たちの活動はゆっくりと、だが確実に最期を迎える人たちの“拠りどころ”になりつつある。
どの人にもどの命にも必ず訪れる死―――
その瞬間をどう迎えるのか、残された時間をいかに生きるのか・・・・・・
「死は生と同じように、自分で選択できるものでなくちゃ。無意味な延命治療に任せるんじゃなく、どうすれば自分らしい最期を迎えられるのか、生きてて良かったと思えるのか・・・。最後を迎える選択肢を持てる街やシステムをつくりたい・・・それがホスピス運動なんです」
ウィル(Will)――そこには「何ごとも自分の意志で」という、静かな決意がこめられている。
ウィルカード発足へ
25年前、結婚で初めて泉北に。「YWCA」でボランティアや平和活動を続けていたある日、ピアノの教え子の父親でもある和泉市の医師、梅田信一郎氏が在宅ホスピスに取り組んでいることを知る。
「一度ホスピスについての勉強をしようということになって、梅田さんに講演をお願いしたんです。そしたら60人以上の人が集まってくれて・・・これをきっかけに毎月講師を呼んでホスピスやインフォームドコンセント、在宅ケア、尊厳死などの勉強をするようになったのが始まりなんです」
当時16万人近くの人が暮らすベッドタウン、しかも開発から30年が過ぎて高齢化が進んでいたにもかかわらず、泉北ニュータウンにホスピス病棟はゼロ。
しかも患者の心を置き去りにしたまま急速に進む医療技術は、“ガン難民”と呼ばれる人たちを生み、むやみな延命措置に対する不安の声が社会に上がり始めていた時期だった。
「勉強すればするほど、自分らしい“尊厳を持った死”を迎えることがどんなに意味があるかを想うようになったんです。何かしたい、自分にも出来ることが何かあるはずって・・・」
翌年、さっそく納得のいかない延命治療や終末期医療に「NO」を表明する「ウィルカード」の発行に取りかかる。
「これを持っていればOKというのではなくて、死を考えるきっかけになるものだと思ってほしいんです。たとえばカードを持つことで『延命はやめてほしい』という自分の思いを家族と話し合いまた医師にも理解してもらう。医師と患者は対等な関係で尊重しあわなければならない。互いにコミュニケーションをとってこそ、治療の自己決定もすることができるのです。」
ホスピスは人と人とのつながり
いつしか会員も300人を超え、老健施設「いずみの郷」や「阪和第二泉北病院」ホスピス病棟などでのボランティアもスタート。そのなかでホスピスというのは建物だけじゃない、人と人とのつながり、コミュニケーションだということを痛感する。
「本人はもちろんだけど、もっと助けを必要としてるのはその家族。みんな介護の疲れや不安、寂しさなどでもう疲労困ぱい・・・そんな人たちに『大丈夫、患者さんのそばで手を握ってあげるだけでいいのよ』と寄り添うのも私たちの大切な役目なの」
5年前からは自らが所有していたマンションの一室を「マーガレットハウス」と名づけて提供。医療・介護の啓発の勉強会・セミナー・講演会を行う一方で、ガン患者の会「ウイルほのぼの」や電話相談、高齢者が憩うシニアサロンのスペースにもなっている。
発足から14年が経って社会は大きく変わり、泉北にも数ヶ所のホスピス病棟が誕生するまでになった。ウィルをはじめとする市民の声は今、大きなうねりとなって時代を変革するキーワードになりつつある。
「でも、まだまだしなくてはならないことがある。超高齢化で増える独居の方たちのためのセーフティネットを作りたい、そして入院しなくても気軽に立ち寄れる『デイホスピス』のような施設ができないか・・・・・・課題はたくさん! いつも時代の一歩先を見つめてアンテナを張っておく・・・それが私の役目なのかも(笑)」
気負わずあせらず、けれど「きちんと時代に添っていきたい」という彼女の意志――それもウィル。こういう市民の活動こそが地域を変えていく起爆剤なのだ。
2010/02/04 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔