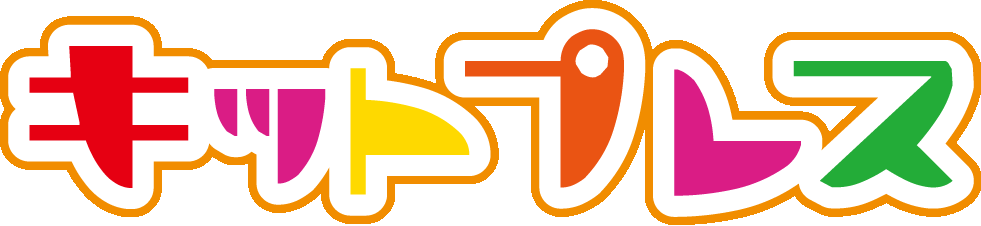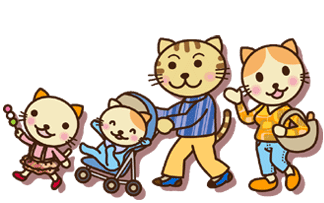バーンスリーという楽器を通じて、インドに恩返しがしたい

File.120
北インド古典音楽 バーンスリー奏者
ぐみ なかぐち たくみ
gumi(中口拓実)さん [京都府在住]
公式サイト: http://000gumi000.blog.fc2.com/

1982年 堺市出身
2000年 堺東高校卒業後、IT企業に勤める傍ら「大阪デザイナー専門学校」に
2006年 インドに渡り、横笛バーンスリーに出会う
2013年 ジャズピアニストとの即興デュオ等を収録したCDアルバム「When it Blooms」を発表。ライブ活動や講師をしながら、関西を中心に各地でライブやワークショップを開催する
「インドが呼ぶ」という言葉があるのだという。
亡き作家・三島由紀夫氏の「インドには行ける者と行けない者がある。そしてインドに呼ばれる時期も、運命的なカルマ(因果)が決める」という言葉からきているらしい。
そして彼はまさしく9年前インドに呼ばれ、バーンスリーという横笛に出会った。
「自分のエゴと向き合うこと、人や自然への感謝や祈り…インドという国は僕にあらゆることを教えてくれたんです」
要領の良さや目に見える豊かさ…そればかりを求める日本とは、対極にあるスピリチュアルな世界。
「インドは僕を成長させてくれた素晴らしいところ。だからバーンスリーという楽器を通じて、恩返しがしたいんです。ひとりでもたくさんの人に、この国の魅力を伝えたい、それが僕の使命やと思うんです」
民族音楽にハマった高校時代
高校時代ハマったのはギターでもなく、クラシックでもない。なんとオーストラリアの先住民、アボリジニの間に伝わる民俗楽器「ディジュリドゥ」だというから、なんともユニークだ。
コアすぎてよくわからないこの楽器、アボリジニが白アリに食べられたユーカリの木を切って作ったもので、1メートル以上もある最古の管楽器なんだとか。
「完全にアウトローですよね(笑)高校卒業してからはグラフィックデザインの学校に行ったんですけど、授業も受けず、廊下でひとりディジュリドゥを吹いてたりするヘンなやつでした(笑)」
そんな自由人ながらIT企業にも就職し、役職もついて普通に働いていた矢先、あるモメごとが起こる。
「会社の上司とケンカになって…どうしても彼のいうことは間違ってる、受け入れられないって押し切り、結局土下座までさせてしまったことがあるんです」
だが、年輩の上司が頭を下げているのを見た瞬間、心が凍りつく。
「あ、オレ何やってるんやろと。いつのまにかサイテーの人間になってるやないかって」
そしてここからの展開がまた、なんとも自由で彼らしい。
「このままここにおったらアカン」とスッパリ会社を辞め、日常を捨ててオーストラリアへと旅立ってしまったのだ。
「いっつも直感で動いてしまうんですよね(笑)それからはアボリジニが多く暮らしているノーザンテリトリーで、ワーキングホリデーを利用して農業を手伝ったり、好きな音楽をやってました。今思えばヒッピーのような暮らしやったんですけど」
それから1年半後、「お金も貯まったし、今度は小さい頃からなんか好きやったインドにも行ってみよかなと」またもや直感に導かれるようにインドに向かう。いよいよ「インドに呼ばれる」時がやって来たのだ。
バラナシで見つけた自分の道
彼が住むことにしたのは、民族音楽を学びたい若者が世界中から集まってくるという町、バラナシ。
1500近い寺院と、あの有名なガンジス川を抱く「これぞインド」という聖なる町だ。
「初めて行った時は、とにかく衝撃!の日々。ガンジス川でたくさんの人が沐浴したり、洗濯してるすぐ横では、毎日遺体を火葬する煙が立ちのぼる。生と死が一緒にある、今まで見たこともないカオスのような場所やったんです」
ここで声楽などさまざまな古典音楽を学ぶうち、いつしか心惹かれていったのがバーンスリーという横笛の素朴な音色だった。
「僕、クリシュナっていう神様が大好きで。インド神話に出てくる英雄なんですけど、クリシュナが小さい頃からいつも持ち歩いていたのが、このバーンスリーだといわれているんです」
ちなみにこのクリシュナ、なかなかハンサムな神様で、笛の音を聞いた娘たちはみな恋に落ちたんだとか。
「バーンスリーは竹の筒に穴が6つか7つ開いてるだけの、とってもシンプルな楽器。シンプルさが魅力なんやけど、それだけに奥が深すぎてメチャ難しい。ごまかしがきかないんです」
しかもインド音楽は、独特の微細な音階やゆらぎが特徴なので、オタマジャクシにできないという難しさがある。つまり音符が無い、人から人へと伝えていくしかないのだ。
だから今も必ず年に3~4カ月は、その腕を磨くためにインドに滞在。「もう日本とインドのどっちが故郷だったか、わからなくなってきました(笑)」
3人の師匠に弟子入りして修業したが、常に教えられることはひとつ。
「ステージには真っ白で上がりなさいといわれるんです。神様に使っていただけるように、無になって体をあけわたす。そのために日ごろから心を整えて、練習を重ねなさいと」
いざという時に力になるのは、どれだけ自分という器を磨けるか…
エゴや欲を捨てて、神にすべてを捧げるという精神世界のなかで、彼も少しずつ変わっていく。
「インドの芸術はみな、神に捧げるためのもの。神という目に見えないもののために、全身全霊で祈りささげる。そんなインドの文化や出会った人たちのおかげで、今の僕があるんやと思うんです」
インドに恩返しがしたい…そのためには、たくさんの人にインド音楽に触れてほしいと、国内だけでなく海外でも無料のワークショップやイベントを行う。
「演奏を聴いた人が少しでもインドに興味を持ってくれたら嬉しい。僕がその入り口になりたいし、インドの魅力をもっともっとたくさんの人に伝えたいんです」
2015/1/12 取材・文/花井奈穂子 写真/ 小田原大輔